活動デザインの越境2025.2.4

2025年2月4日、デザインディレクターの川浪寛朗氏を迎え、九州大学大橋キャンパス デザインコモンにて、未来デザイン学センター主催の講演会「デザインの越境」を開催しました。川浪氏は、2008年に九州芸術工科大学の工業設計学科を卒業後、Studio ShirotaniでKINTOのプロダクトデザインに携わり、その後、日本デザインセンター・原デザイン研究所にて、企業のブランディングやプロモーション、展示計画、サイン計画、プロダクト、建築など、幅広いプロジェクトを担当されました。2020年に独立し、Hiroaki Kawanami Designを設立。プロダクト、空間、グラフィック、広告など、デザインの領域を自由に越境しながら、多彩な活動を展開されています。
今回の講演会では、川浪氏が日本デザインセンターで原研哉氏と共に行ったプロジェクトから、パッションエコノミーと呼ばれる個人の興味関心を起点とした経済の話題まで、幅広いテーマを取り上げ、これからのデザインの可能性について語っていただきました。当日は約50名の方に参加いただきました。
以下、講演の内容から,いくつかのトピックに絞り、ご報告いたします。
― Studio Shirotaniでの経験と影響
川浪氏は、長崎県小浜町でデザイナーの城谷耕生氏と出会い、影響を受けたといいます。城谷氏は、イタリアでプロジェッタツィオーネ(Progettazione)の巨匠アキッレ・カスティリオーニやエンツォ・マーリに学び、帰国後は、消費主義社会の企業利潤のためではなく、職人のためのデザインとは何かを考え、活動されていた方です。もので溢れたこの社会において、全く新しいものを必ず生み出そうとするよりも、既にそこに素晴らしい技術があるならば,それを活かし、育むことが、より良い製品をつくり、職人とその技術を救うことができるという考え方に共感し、デザイナーとしての姿勢に影響を受けたそうです。
また、大分県別府市での竹工芸の職人とのプロジェクト(BAICA)などを例に、社会性や倫理性に富んだ創造の仕方について具体的にお話しいただきました。さらに、仕事を進める中で「本当にそれをすべきなのか」と立ち止まり、問い直す姿勢の大切さについても言及されました。
※プロジェッタツィオーネ:消費主義社会の企業利潤のためのデザインではなく、社会性のある創造と市民全般への教育を使命とする倫理性に富んだイタリアで育まれたデザインの考え方。
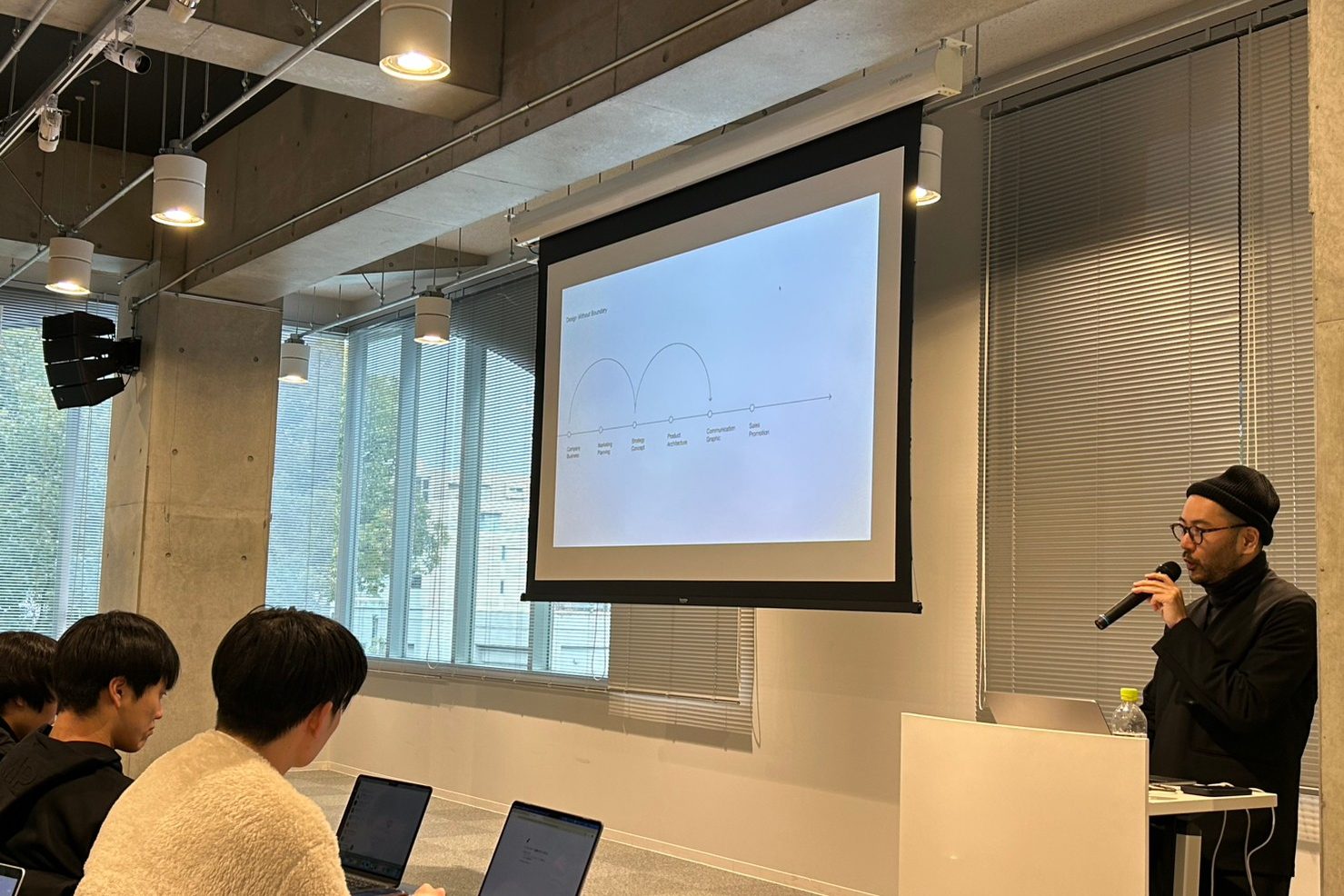
― 独立後の活動とパッションエコノミーについて
日本デザインセンターでの仕事のお話の後、独立後の活動についてもお話しいただきました。アウトドアと都市生活の相互関係をテーマに活動を開始し、hxo design(台湾)の日本展開を開始。また、山中湖のサウナ施設《CYCL》のクリエイティブディレクターを務められています。
さらに、カナダのアウトドアブランド アークテリクス の新宿ブランドストアの広告キャンペーンでは、「NO EASY ROUTE(近道はない)」というモノづくりの姿勢を表現する映像を制作。製造過程で使用されなかったゴアテックス素材に手刷りのシルクスクリーンを施し、JR山手線などの中吊り広告として展開しました。広告終了後には、これらの素材をアップサイクルして新たなプロダクトに生まれ変わらせるプロジェクトも紹介されました。
また、デジタルツールの発展により、個人が発信し、オンラインで販売できる時代になったことにも言及。パッションエコノミーの概念を紹介し、自身のものづくりの姿勢と重ねながら、「デザインができること」について語りました。 本講演を通じて、参加者はこれからの時代のものづくりの在り方や自分のキャリアについて考える機会になりました。川浪氏の経験を通じ、どうすれば領域を越境しながらデザインができるのか、どうすれば様々な感覚を養い広い視点を持てるのかなどについて考える充実した時間になったと思います。

