活動大学建築アーカイブの挑戦、活動と課題の共有2023.11.1

研究責任者:芸術工学研究院 准教授 井上朝雄
キーワード:大学建築アーカイブ、建築資料、葉祥栄アーカイブ
2023年11月1日、未来デザイン学センター主催、九州大学葉祥栄アーカイブ[i]共催で、「大学建築アーカイブの挑戦、活動と課題の共有」と題して、大橋キャンパスデザインコモンにてシンポジウムを開催した。シンポジウムは2部構成とし、第1部は、CCAから、コレクション部門の副ディレクターのMartien de Vletter、アーキビストのAnna Haywoodの2名を招へいし、基調講演をお願いした。第2部では、日本の大学の取り組みからは、金沢工業大学 勝原基貴先生、京都工芸繊維大学 三宅拓也先生、京都大学 齋藤歩先生、法政大学 藤本貴子先生、21世紀美術館 本橋仁氏、神奈川大学 六角美瑠先生、九州大学からは、岩元真明先生、井上が参加した。
昨年、伊東豊雄の初期の建築資料がカナダ建築センター(CCA)へ寄贈されたのが話題になったように、日本の建築アーカイブは危機に瀕している。2013年に国立近現代建築資料館が開館したが、限られた予算の中では状況は変わらず、現状のままであれば、今後、日本を代表する建築家の建築資料が海外に流出するのは免れないだろう。そのような状況の中、さまざまな大学において、建築家のアーカイブを構築し建築資料の散逸防止に取り組む事例が増えてきている。それらの取り組みのひとつひとつは小さなものであるが、まとまることによっていずれ大河となるように、まずは、国内大学におけるそれぞれの取り組みについて活動と課題を共有するシンポジウムを開催することとした。
Martienは、Activities of Canadian Centtre for Architecture、と題して、CCAの概要と2013年にCCAで開催されたArchaeology of the Digital展での葉祥栄氏との思い出話を、Annaは、The Shoei Yoh archive as a Case Study for Working with Hybrid Collectionsと題して、CCAに収蔵されている葉祥栄の建築図面および資料のアナログとデジタルの扱いについて講演いただいた。
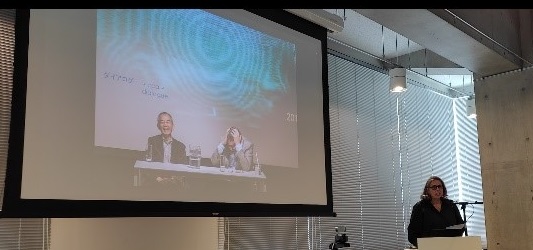
続く日本の大学では、金沢工業大学の勝原先生が、Establishing a circulation of knowledge around architectural materialsと題して金沢工業大学での建築アーカイブの取り組みを、京都工芸繊維大学の三宅先生が、Architecture Collection of the Museum and Archives, Kyoto Institute of Technologyと題して京都工芸繊維大学での建築アーカイブの取り組みを、京都大学の斎藤先生が、Research Resource Archive, Kyoto University and Architectural Recordsと題して京都大学での建築アーカイブの取り組みを、法政大学 藤本先生がTeaching with Drawings of Hiroshi Oheと題して法政大学での建築アーカイブの取り組みを、21世紀美術館の本橋氏がWaseda Architecture Archivesと題して早稲田大学での建築アーカイブの取り組みを、神奈川大学 六角先生が、Rokkaku Kijo: His Philosophy, Works, Drawings and Modelsと題して神奈川大学での建築アーカイブの取り組みを、岩元先生が、Shoei Yoh Archiveと題して九州大学での建築アーカイブの取り組みを、井上が、Shoei Yoh Digital Restorationと題して、消失した葉祥栄の建築のデジタル復元について講演した。 いずれの大学においても、活動資金の不足、活動スペースの不足、マンパワーの不足という三重苦に悩んでいることがわかった。けっして展望は明るくないが、課題やノウハウを共有できたことは、大学において弱小アーカイブに取り組むわれわれにとっては小さいけれど大きな一歩となった。
[i]九州大学葉祥栄アーカイブ:九州大学大学院芸術工学研究院に設立された、建築家葉祥栄の建築資料を収蔵するアーカイブ
